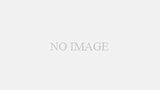3年後(2028年3月)に公務員退職を目指すブログ(16歩目)
足をお運びいただきありがとうございます。
今日は今まで教育活動とはされていない「部活動」が、学校の現場から何故切り離されていなかったのかということを考えてみたいと思います。
なぜ今まで学校教育から学校教育の位置付けではない「部活動」が切り離されなかったのか!それは、部活動で学ぶことは「日本のビジネスマインド(仕事観)の縮図」であるからと言えます。
運動系や団体種目での部活動経験者は「就職に有利」と言われたり、進学の際の内申点にプラスにはたらくと言われています。それは学校教育の中で「組織」を学ぶのは「部活動」くらいしかないからです。テストや各教科の授業は取り組む生徒(人間)の個人技能の修得のための取り組みです。また学校行事などでクラス単位やグループ単位での短期的な活動はあるものの、3年間同じ部活動(組織)に所属して、目標に向かって練習(仕事)をする長期的な取り組みは、学校現場では部活動しか存在しません。チーム(組織)でなしとげる精神を身につけるために
部活動は先輩・後輩と言った「年功序列制」になっていて、ひとつの部活動3年間やりきる「終身雇用制」、文武両道をうたって「勤勉」であることを望みます。また複数部活動加入禁止というルールは「副業禁止」、練習時間の確保といった「長時間労働」と結びつくことができるのではないでしょうか。
このことから日本の中等教育において、日本のビジネスマインド(仕事観)や組織を学ぶのは、
「部活動メソッド」しかないのです。これが今まで学校教育から部活動が切り離せなかった理由のひとつだと私は考えます。
このビジネスマインド(仕事観)を学ぶために、教員の休日や残業時間、家族との時間などが犠牲となりながら、今まで続いてきました。それが先生方の働き方改革により、今まで微妙であった部活動の教育としての位置付けに疑問を持つ人が多くなったため、「部活動の地域移行」が進み始めることとなりました。
部活動内でも同じことが起こっており、「休養日の適切な設定」や「長時間の練習をさせない」はまさに「働き方改革」とも言えると思います。
部活動の地域移行が進むことは、日本のビジネスマインド(仕事観)が変わっていくキッカケになリえると考えます。