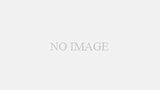3年後(2028年3月)に公務員退職を目指すブログ(20歩目)
足をお運びいただきありがとうございます。
部活動の地域移行の取り組みのひとつに「拠点校」制を活用している地域があります。
「拠点校」とはひとつの街に、3,4校ある中学校の部活動を拠点校となっている学校でまとめて実施して、ひとつのチームとして試合に出場するという形です。
合同チームと似ていますが、合同チームの場合は試合や遠征があるとそれぞれの学校から引率する教員が出てきて、試合や遠征を行います。 拠点校の場合は3,4校ある中の拠点校の監督が試合や遠征の引率を行うという形です。合同チームの場合は合同となった学校の数だけ教員が引率し、拠点校制は引率者が1人と、遠征での教員の引率人数、引率旅費を抑えることができます。
そのような制度のため部活動の地域移行の取り組みとしては、導入しやすい制度となります。
また部活動の指導をしたいと考える先生にとっては、生徒募集などの煩わしさもなくなり、メリットが多くなります。
教員の働き方や引率費などのメリットがある反面、拠点校制の部活動におけるその地域の競技人口は必ず減る形となります。
拠点校とは話は違いますが、以前小学校のバレーボールで男女混合チームで試合に出場できる制度ができました。その小学生が中学生、高校生と競技を続けたとしても、小学校チーム時点では男子3人、女子3人で試合に出られていましたが、中学・高校は男女別にチームを作らなくてはいけないため、小学校でのバレーボール経験者が二つに分かれ、中学・高校ではチームが成り立たなくなってしまったという地域もありました。
拠点校制になるとたとえば野球やサッカーなどでは、3~4校の中学校で野球なら9名、サッカーなら11名と試合に出場できる人数程度しか集まらず、その後の高校でその経験者たちがばらけた結果となると、高校ではチームが成立しないという現象が発生すると予想されます。
子供の数が減少して、合同チームや拠点校チームが増えると、その地域の競技人口が減ってしまう流れになります。
また拠点校制には地域や街の大きさも重要です。大きすぎる街では拠点が作れず、街に一校の中学校しかない地域も拠点を作ることはできません。適切な街の大きさ、人口数、中学校数が必要になります。
部活動地域移行の一つの取り組みとして、「拠点校」制で成功している地域はある反面、その「拠点校」制を導入できない地域もあります。
今後の動静も注視しながら、「拠点校」の地域移行を見守っていきたいと思います。