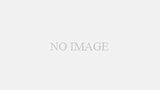3年後(2028年3月)に公務員退職を目指すブログ(18歩目)
足をお運びいただきありがとうございます。
今日は現日本におけるマイナースポーツの現状について考えていきたいと思います。テーマはタイトルの通り、「日本のスポーツ・スポーツ協会は、ほぼボランティアにより支えられて、多くの人(先生方)の犠牲によって成り立っている」という内容です。
オリンピックでも花形種目である陸上競技を見てみると、都道府県の協会は資金不足に悩み、役職につく人は教員や昔競技をやっていたり教えていたりした一般のボランティアの方で、そこに関わる人はほとんどが無報酬で仕事を行っています。競技会では多くの審判が朝早くから日が暮れるまで、お昼のお弁当と少額の交通費を支給されるーぽ程度で働いています。このように多くの人の善意(犠牲)によって成り立っている状況が、結果として競技の普及・発展や指導環境の向上にストップをかけていると考えています。
私はこの現状を変えたいと思い、スポーツ指導や運営を「ビジネス」として成立させて、教える側も教わる側もwin-winの関係になれるように起業を目指しています。
地域移行が進んでも、保護者から集める会費や月謝が少なければ、指導する監督やコーチたちがボランティアで働かなくてはいけなくなり、教員の働き方改革のように指導への不満が出て、結果良い指導ができなくなってしまいます。そのため指導者が適正な報酬を得られる環境が必要となるわけです。指導に似合った報酬にすることにより、教える側にも責任が生まれ、質の高い指導が提供でき、結果的に競技レベルも上がってきます。
先生方の時間や収入といった犠牲で成り立っていた部活動制度を「地域移行」というキッカケで改善していかなければいけません。
それにはハードルが多いですが、少しずつでも前に進めるよう、スポーツ指導の価値を高め、持続可能な取り組みに作り替えていく必要があります。このブログを書きながらその方法を模索し続けます。